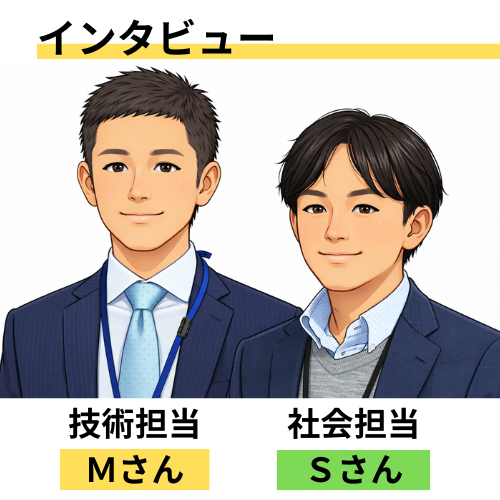前回は、社会と技術の準備員よりお話を伺いました。
※ 第4回 社会と技術が描く愛総中 ~体験してワクワク、成長促す~
※ 第3回 英語と家庭科が描く愛総中 ~問いかけ考え、幸せを創る~
※ 第2回 数学と保健体育が描く愛総中 ~関わり考え、興味を持つ~
5回目の今回は、愛総中準備員の理科担当Nさん・K2さんと、美術担当Dさんからお話を伺います。Nさんは愛知総合工科高校の開校当初から同校に勤務されており、K2さんとDさんは中学校教諭として勤務されています。

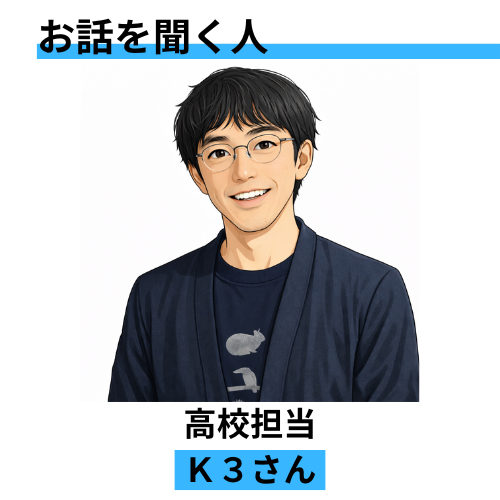
――入試も終わり、いよいよ開校まであと2か月となりました。今の率直なお気持ちを教えてください。
Dさん:「ワクワク」の一言に尽きます。入学の準備をする子どもたちが、新しい文具や教材を手に取って、「私、この定規買ったよ」などと嬉しそうに名前を書いている姿を想像すると、私も同じようにワクワクしてきます。私たち準備員も、準備室で真新しい教材を眺めたり、みんなで「これどうやって使う?」と触ってみたり、レクチャーし合ったりしているんです。その時の準備員の表情が、本当に明るくて楽しそうで。やはり、これから新しいものが始まるとき特有の、非常に良いエネルギーに満ちた状態にあると感じています。
K2さん:そうですね。これまでは子どものいない中で企画を進めてきましたが、実際に子どもたちが加わることで、それがどう形になっていくのか楽しみです。説明会などを通して、すでに特定の分野に関する興味関心や知識を持った子どもたちが集まってきていると感じています。そうした子どもたちと私たち教員が交わることで、お互いに成長していける環境ができているのではないかと感じています。自分の知らない世界を子どもたちから教えてもらい、教員自身も成長できるのではないかという期待があります。

Nさん:私はお二人とは少し違った視点なのですが、実は愛知総合工科高校の開校当時を経験しています。その時は、開校前の準備にはかかわっておらず、開校1年目から化学の教員として勤務しました。そのため、高校の教育理念の理解を深めるのと同時進行で、4月から授業を行ったため、「工業高校で普通科目の理科に何ができるのか」という不安に加え、物品もカリキュラムもどうなっているか分からない、まさにゼロからのスタートでした。正直に言いますと、普通科出身の教員が工業高校に来て、新しい環境・文化で、「とにかく考えて即実行する」ような、手探りの状態でした。
――それは壮絶なスタートでしたね。今回は違いますか?
Nさん:全く違います。今回は、私を含め準備員みんなで積み上げてきた「自律・自主・好奇心」という確固たる教育理念を1年前から共有できています。教科の数が限られ、小規模であるからこそできることだと思います。そして、その理念に共感し、自分自身も入学生のような新鮮な気持ちで、「この学校でどんなことができるだろう」と期待しています。生徒の将来や人間形成に関わる大事な部分に携われることへの前向きな気持ちでいっぱいです。自分自身も変わらなければいけない部分はあると思いますが、生徒と共に変化し、成長したいと思っています。
――皆さん、期待と楽しみで胸がいっぱいという様子ですね。では、理科としては、どのような学びを提供したいと考えていますか?

K2さん:私は、理科を学ぶ意義は大きく二つあると考えています。一つは、自然現象を知ることで「世界の見え方が変わる」ということです。今まで何気なく見ていた空や星も、その仕組みを知ることで全く違ったものに見えてくる。知ることで視座が高まり、違う切り口で世界を見られるようになる。それが理科を学ぶ面白さであり、人生をより良くすることにつながると思います。
――もう一つは?
K2さん:知識そのものよりも「考え方」や「思考の技」を身につけることです。例えば、実験でデータロガーなどの新しい機器を使う際、単に使い方を覚えるのではなく、「なぜそれを使うのか」「どう分析すれば探究につながるか」という思考のプロセスを大事にしたいと考えています。理科を通して学んだ「見方・考え方」は将来絶対に役に立ちます。例えば、ワープロソフトが変わっても文章作成の論理が変わらないように、プログラミング言語が変わってもアルゴリズムの思考は変わらない。このように道具が変わっても対応できる「土台」を作りたいのです。
――工科高校にできる附属中学校だからこそ、その「思考の技」が重要になるのでしょうか?
K2さん:その通りです。将来的に専門的な理工学を学ぶ多くの生徒たちにとって、ただ知識として「やり方」を知っているだけでは不十分です。公式を知っているだけでなく、それをどう使うか、どう自分で思考するか。そうした汎用的な力を、中学校の理科でしっかりと養いたいと考えています。
Nさん:私も同感です。加えて、理科では原子や分子など「目に見えないもの」を扱いますが、それを言葉やモデルで説明できる力は、将来エンジニアとして見えない現象を扱う際や、他者に概念を伝える際にも不可欠な力になるはずです。実は、工業科の先生方の話を聞いて驚いたことがあるんです。ものづくりにおける安全管理一つとっても、挨拶の声の大きさから徹底されています。それは単なる精神論ではなく、「工場では機械音が大きいため、声がかき消されないように大きく発声する必要がある」という、命を守るための合理的な理由があるんです。
――挨拶一つにも、科学的・合理的な理由があるんですね。
Nさん:そうなんです。「なぜそうするのか」という背景や理由を知ることは、まさに理科的なアプローチです。そうした「理由」を含めて理解し、説明できる力を育みたいですね。高校生がスピーチなどで自分の言葉でしっかりと語れるのは、そういった背景理解があるからだと感じています。中学生にも、現象の背後にある理屈を面白がりながら学んでほしいですね。
――専門知識の土台となる「思考の技」や「表現力」を磨くということですね。では、美術についてはいかがでしょうか?
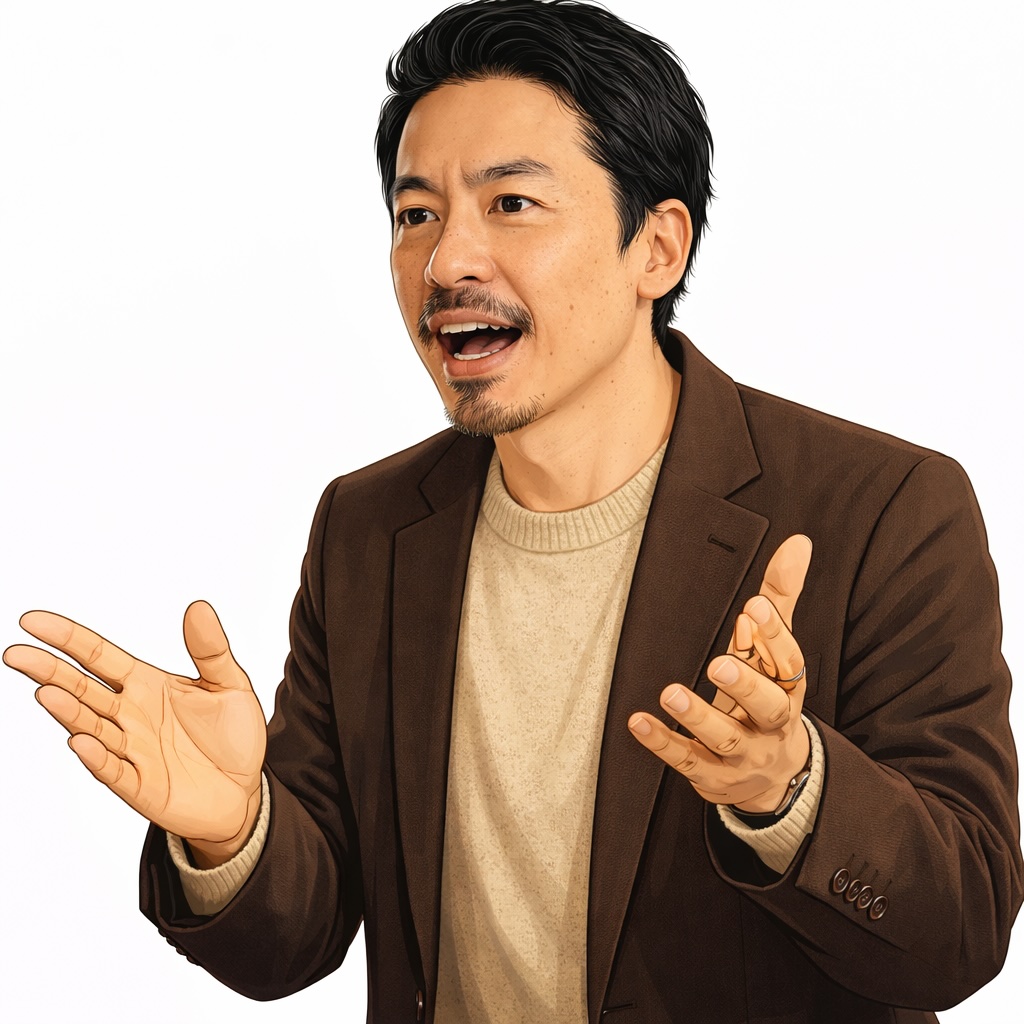
Dさん:私はあえて「鑑賞」に力を入れたいと考えています。ものづくりにつながる学校なので「作ること」は当然行いますが、料理に例えるなら、美味しい味を知らなければ美味しい料理は作れませんよね。「味わう」経験、つまり鑑賞を通して、先人が作ったものや級友の作品、本物に触れることで、「自分はどう作りたいか」というゴールのイメージを持つことができます。
――ものづくりにつながる学校だからこそ、作る前の「味わう力」が大切だと?
Dさん:はい。自分の知識や経験だけでは到達できないゴールを知ることで、そこから逆算して「何が足りないか」「どうすればいいか」を考えることができます。今の技術教育において、ともすれば「作らせて終わり」になりがちな部分に対し、美術が「良さを知る」「味わう」部分を担うことで、結果として質の高いものづくりにつながると考えています。例えば、料理で塩加減や焼き加減を調整するように、「ここはもっとこうしよう」「次は砂糖を入れてみよう」といった試行錯誤のプロセスを、味を知った上で学んでほしいのです。
――なるほど。「良いもの」を知らなければ、そこを目指すこともできないわけですね。
Dさん:その通りです。
Nさん:私自身、絵を描くのが得意なわけではありませんが、美術館などで作品の背景や作者の意図を知ると、「なるほど、だからこういう色使いなんだ」と深く納得でき、見え方が変わります。
Dさん:私は、美術教育の究極的な目標は「人生を豊かにすること」だと思っています。例えば、毎朝ネクタイを選ぶ楽しみや、街中のコンクリートの打ちっぱなしを見て「面白い表情だな」と感じたり、夕焼けを見て「綺麗だな」と思えたりする。そんな日常のふとした瞬間に美しさを感じる感性は、その後の人生観を大きく変えるはずです。
――理科も美術も、工学やものづくりの質の向上に直結する視点がありますね。
K2さん:お話を聞いていて、理科と美術は似ているなと思いました。理科も「知ることで見え方が変わる」教科です。背景にある理論や、自然の法則を読み解くことで、これまでただの現象だと思っていたことが意味のあるものに変わる。その知的好奇心は、教科を越えて共通していますね。
――理工系の興味を持って入学する生徒が多い中で、あえて多様な教科を学ぶ意義をどう捉えていますか?

Dさん:理工学的な興味に特化している子こそ、中学校という義務教育の段階で、美術や他の教科に触れることに大きな意味があると思います。一度視野を広げ、自分の専門外の領域に目を向けることで、結果として自分の武器が強化されたり、新しいヒントを得たりすることができるはずです。「美術は苦手だな」と感じたとしても、それもまた一つの発見であり、成長です。
Nさん:そうですね。失敗も含めて多様な経験をしてほしいです。社会に出れば、自分の経験則だけでは対応できないこともあります。たった一つの成功例しか知らないよりも、中学校での「チャレンジ」と「失敗」、そしてそこから「なぜ失敗したのか」を考えて改善していく経験が、将来社会で学び続ける力につながると信じています。
Dさん:学びの過程には矛盾があることもあると感じています。人生を豊かにするための勉強なのに、それで苦しんでしまうこともある。だからこそ、この学校では「探究」や「多様な経験」を通じて、学ぶこと本来の楽しさと価値を再発見してほしいですね。
K2さん:もし理工学的な興味が途中で変わったとしても、それはそれで素晴らしいことです。重要なのは、一つのことに没頭する経験や、多様な視点を持つこと。それが人間形成につながると思います。私たちの想像を超えて、生徒たちがまだ誰も拾っていないような「ヒント」や「種」を見つけ、それを理工学的な視点と掛け合わせることで、新しい価値を生み出してくれるのではないかと期待しています。それが、誰も見たことのない「新しい風」になる気がします。
――専門性を深めるためにも、一度視野を広げ、自分自身を「鑑賞」し、世界を多角的に捉え直す。そんな知的な探究が愛総中で展開される予感がしました。私たち準備員も、ワクワクしながら、新しい学びの最終準備を進めています。愛総中の理科・美術の授業についてお話しいただき、ありがとうございました。
Nさん・K2さん・Dさん:ありがとうございました。