8月23日(土)に愛総中の学校説明会を開催しました。
そこでは、総合的な学習の時間を市町村立の中学校よりも増やし、チャレンジ100を軸とした体験的かつ探究的な学びが特徴であることを紹介しました。そして教科については、数学・理科・英語で少人数授業が展開されること、英語でグローバルプログラムを実施することをお伝えしました。
時間の都合により、説明会では上記の内容しかお伝えすることができませんでしたが、このウェブページにて各教科の準備員の思いをインタビュー形式でお伝えすることで、愛総中における学びの全体像を紹介したいと思います。
初回の今回は、愛総中準備員の音楽担当Bさんと、国語担当Kさんからお話を伺います。お二方とも、中学校教諭として勤務されています。
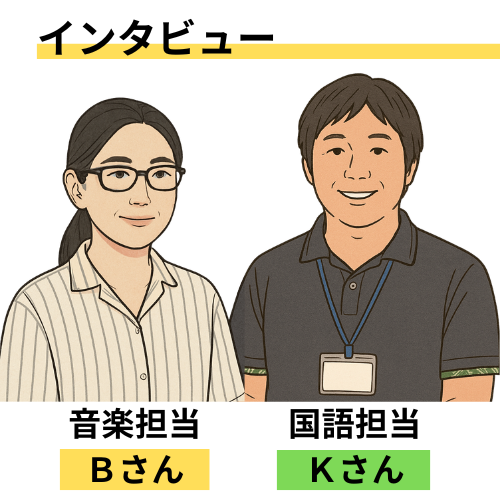

――まずはじめに、先日行われた愛総中説明会の感想を教えてください。
Kさん:科学技術やものづくりに興味関心をもつ子どもたちが参加してくれるんだろうなと予想はしていましたが、本当にそのような子どもたちが数多く来てくれて、安心しました。特に校内見学で、興味をもった機械や説明に足を止め、じっと見たり聞いたりしている様子や、家族や友人・先輩と話している様子から、自分から進んで説明会に参加してもらえていると感じました。
Bさん:私も、子どもが保護者の手を引っ張りながら、校内見学に興味を持って参加していただいている様子を見て、自分の意志で動ける子どもが多いと感じると同時に、保護者の方もお子様の興味関心を理解して、本校を選んでいただいていると感じました。
――入学を期待する児童像と、実際見学いただいた子どもたちが一致したということですね。では、そのような子どもたちに、教科「国語」では、どのような学びを提供したいと考えていますか?
Kさん:チャレンジ100に組み込まれる国語的な内容もあるとは考えていますが、授業の中では、単元を通して答えのない課題に取り組み、自分なりに考えをまとめ、発信できるようになって欲しいと考えています。
――例えば?
Kさん:スピーチやプレゼンテーション、レポート、さらにはバズセッションみたいな。パターンはいろいろありますが、自分で考えた意見をまとめて発信することに留まらず、根拠をもって語れるよう支援し、授業を行いたいです。
――このような考えに至ったのはなぜですか?
Kさん:校内見学では、理工科の生徒をはじめ、高校生が自分の取り組んでいることを自分の言葉で話している姿を見て感動しました。私が普段教えている中学生が、高校へ進学し成長する姿を初めて見ることができましたし、実社会に近い工科高校だからこそ、伝える力が身についているのではないかと感じました。そのため、中学校で伝える力を伸ばすことで、高校進学後、さらに成長することができるようになるのではないかと考えたからです。
――では、国語の授業で気を付けていること、気を付けたいと考えていることはありますか?
Kさん:もともと読むことと書くことのバランスが大切だと考えていて、気を抜くと、読む力の方に偏ってしまうのです。
――それはなぜ?
Kさん:文章の読み方にはある程度答えがあって、こうするといいとか、合っているのか間違っているのかの判定がしやすいからです。評価しやすい力であるから、成長を実感しやすく、達成感も得られやすいと思います。
――「読み=インプット」、「書き=アウトプット」とイメージすると、インプットした知識は正誤が明確ですね。書き出したアウトプットは、その過程も大切だと思いますが、どのような授業を目指したいですか?

Kさん:少しでも、何の役に立つのか、今自分は何を学んでいるのかについて実感できる授業にしたいです。たとえば、「今日、国語の時間に何をやった?」と尋ねた時、「ごんぎつね」というようにタイトルがかえってくるのではなく、ごんの心情をどう読み取ったのか、情景描写や語りの視点がどうかという中身が返ってくるようにしたいです。それが、答えのない問いにぶつかっていくことにつながると思います。このようなやり取りを通して、授業だからこそ育てられる実践的な力を重視していきたいなと考えています。
――続いて、教科「音楽」についてお聞かせください。
Bさん:逆説的な言い回しになってしまうのですが、工科高校の附属だからといって、特別なことをやる必要はなく、むしろ、これまでの授業で培われてきた古き良き音楽のアナログ的なものを意識的に大切にすることで、子どもたちの感性の部分に強く訴えかけることができると考えています。
――音楽のデジタル化という単語が出るかと思ったのですが、逆ですね。そう考えるのはなぜですか?
Bさん:音楽は情操教育であり、人間の根本の部分で、人の感じ取る力や、あるがままをそのまま受け入れる力を育むことだと思っています。現代の子どもたちは、生まれた時からスマートフォンがあり、デジタル化されていることが普通で、アナログなことの方が新鮮であり、特別なことになり得ます。
音楽の分野では、様々な楽器がサンプリングされていますが、本物の楽器を知ることが本来土台となり、音楽教育として学校だからこそ提供できる価値だと考えています。この本物の楽器に触れることが、嘘偽りない経験として生かされるはずです。
――「本物のものづくり」を体験する学校だからこそ、楽器も本物に触れて感性の土台をつくりたいということですね。とても共感します。
Bさん:そうなんです。本物を知らずして作れないじゃないですか。日常生活は音で溢れていて、その日常にどうやって音を活かしていくのか考えること。これは子どもたちが考えることになりますが、より多く本物が存在していた方が、この子たちの役には立つはずです。
合唱だけが音楽じゃないし、器楽だけが音楽じゃない。風の音とかも音楽であり、音として発せられる言葉もすべて音楽だと思っています。
――音として発することについて、もう少し詳しく教えてください。
Bさん:個人の感性や楽曲の機微、そして言葉の中にもイントネーションがあって、音の発し方一つで全く感情が違ってきます。そして、それを音に乗せてどういうふうに展開しているのかを知ることは、とても楽しいと思います。

例えば、自分に還元させると、朝何気なく交わす「おはよう」っていう、この「おはよう」の言葉一つでも、言い方を変えたら相手がどんな受け取り方をするのかとか、状況によってその表情と言葉とリンクしなかったら違和感を感じるだろうなと想像することから、歌う時にも表情が必要だと気付く。こういう本当にシンプルな人間の所作、感情を感じ、自分の在り方を考えてほしいと思います。
――説明会の中でAIが作曲した楽曲が流れましたが、どのように感じられましたか?
Bさん:音楽を手軽に作る親しみやすいツールという意味では、ありなんじゃないかなと思っています。もちろん和声学的には変だなと思う部分や、進行がおかしいなって感じるところもありますが、それは一般の人には全く分からないレベルかもしれません。それを使う側の問題じゃないかなって思っています。
また、AIがあるからアナログが消えるわけではないし、アナログが正しくてデジタルがダメということでもない。両方がそれぞれあって、それぐらい違うジャンルとして私は受け止めています。
――使う側の問題という言葉がありましたが、国語的にはどう見ていますか?
Kさん:AI以外のツールを使う時も同じなのですが、何の作業をさせているのかを把握することが大切だと考えています。自分自身は考えることをして、生成AIにはその整理やまとめを依頼しているとか。あくまで人間が使う側でなければならないと思います。
――人間が使う側であるとは具体的に?
Kさん:AIが万能のツールだと思っている子がいると思っています。それは答えだけを出してくれるから。本来なら、ある一定の手順を踏む過程を経て、答えが導き出されるのですが、生成AIではそこがブラックボックスになっている。そのため、出てきた回答に対して自分で正誤の判断をする必要があるはずです。しかし、まだ思考の過程や、経験の浅い子どもたちにとって、正誤の判断は難しいことだと思います。
国語では、様々な題材を扱って、初めは型として思考の過程を身に付けてほしいと思います。そうすれば、自然と深く考えられるようになり、答えのない問いに対しても、自分なりの考えを導き出せるようになると考えています。

Bさん:音楽も同じように、最終的に表現される音は自由であるため、答えのない問いに向き合う教科だと思っています。だからこそ、これをやったらこうなるなどの予測を体験から感じ取ったり、失敗する経験から学んだりしてほしいです。
――答えのない問いに取り組むという共通するゴールがみえてきましたが、その過程で求める姿勢があったら教えてください。
Bさん:とにかく表現、感じていることを表に出してほしい。それを言語化できないこともあるとは思うけれど、何かが出てくれば、それをきっかけに「あなたはどうしたい? どこに進みたい?」など支援することができます。しかし、感じることを代わってあげることはできません。
Kさん:国語でも、考える型は伝えることができますが、どの型を使うのか、それがうまくできなかったときどうするかは、本人が考えなければならないことだと思います。あなたが何を感じて何を書きたいかを重視するため、中身に関してこちらがアドバイスすることはできないと考えています。
――今回お二人のお話を伺っていて、学びや成長の段階を表す「守破離」という言葉が浮かんできました。多様な興味を持つ生徒が、多様な地域から集まる愛総中だからこそ、型を伝えて、自分でそれをどのように活用するか考え、そして自分の想いを表現できるようにしたい。そんな先生方の思いを感じることができました。
愛総中の国語・音楽の授業についてお話しいただき、ありがとうございました。
Bさん・Kさん:ありがとうございました。
