前回は、国語と音楽の準備員よりお話を伺いました。
2回目の今回は、愛総中準備員の体育担当Gさんと、数学担当Sさん・Tさんからお話を伺います。GさんとTさんは、中学校教諭として勤務され、Sさんは愛知総合工科高校教諭として勤務されています。
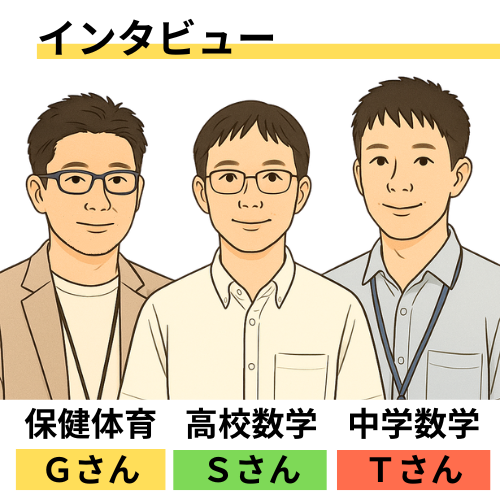

――愛総中の開校準備員となり6か月が経ちました。これまでを振り返っていかがですか?
Gさん:4月に開校準備員として愛知総合工科高校に来たときは、新しい学校を作るという目標はわかっているけど、どうやって進んでいくのか本当に全くイメージがつかなくて、靄がかかったような状態でした。しかし、準備員会の回数を重ねるごとに、具体的な学校像ができてきて、少しずつその靄が晴れていった気がします。そして何といっても、夏の説明会で実際に愛総中に関心を持つ児童・保護者の皆様を前に今まで準備してきたことを具体的な形として説明し、しかもご理解いただいている雰囲気を感じた時、一気に靄が晴れた気がしました。
――特にどのようなことが伝わったと感じましたか?
Gさん:愛総中のビジョンと成長した生徒像です。児童・保護者の皆様も、私の4月の気持ちと同じで、新しい学校ができることは知っていて、今回興味を持って参加いただいたと思います。説明後の学校見学で見た子どもたちの表情や様子が、これに興味がある、これすごく好きみたいに立ち止まって、目をキラキラさせていたことから、説明と見学が結びついて、正しくご理解いただけたと感じました。私が担当した場所では、溶接アートが展示されていて、皆さん釘付けでした。何か作りたいという欲求があるからこそ、このような様子が見られたのだと思っています。
Sさん:私は、もともと愛知総合工科高校で働いていることもあり、この敷地内に中学校ができるとどんな感じになるのだろうと、不思議な感じがしていました。しかし今、模様替え工事が進み、いろいろなものができていくのを見ると、本当に高校の中に中学校ができるんだという実感に変わってきました。
そして、中学校の先生方と一緒に愛総中のことを考えていく過程で、自分の知らなかった義務教育としての中学校の在り方を知り、話し合う中で高校との違いをお互い理解して、より良い学校を創りあげようと盛り上がって議論ができることが楽しい。これまで準備員会を積み重ねて、1つのチームになってきていると感じています。
あとやっぱり、説明会で小学生の子どもたちの姿を見て、来年の4月に生徒が入学するイメージが自然と湧いてきて、より中学校ができる実感が強くなりました。
Tさん:この準備員という仕事は、今まで教員として経験したことのないことであると同時に、多くの先輩方も経験したことのないことなので、挑戦したいという気持ちが第一に出てきました。しかし、4月の第1回の準備員会では、はじめましての人がたくさんいたり、これから何をしていくのかが全く見えなかったりで、ものすごく緊張していたことを記憶しています。もちろん今も緊張しています、なんならずっと緊張しています。本当に緊張しない日はないです。
でも、準備員の方と様々な話題について話し、高校の工業科の学びを体験させていただく中で、この経験をプラスに変えたいという思いが生まれました。
――実際にプラスに変わったと感じたエピソードはありますか?
Tさん:子どもたちのために準備員会で議論や研修を行っているのですが、自分自身のこれからの教員人生が豊かになる半年間だったと、今振り返ると思います。まず、理工科で体験したテンセグリティなど、初めて触れた言葉や、「探究」という、これまで知っている言葉であっても「課題発見⇔仮説⇔検証」というサイクルで回す過程であることを具体例から理解し、自分の知識を上書きすることができました。それにより、現在の赴任校でも、生徒の自律的な学びを目指して、授業改善・試行錯誤をおこなっています。特に工夫したいことは、子どもたちの興味関心と数学とを結びつけることです。テンセグリティであれば図形と結びつけることができるなど、教科書には載っていないけれども、実社会における数学の活用例などを授業に関連付けたいと考えています。
まだまだ、知識は足りないですが、この愛知総合工科高校で未知なるモノ・コトに触れて私自身の想像力が刺激されている気がします。もしかすると、このような体験的な学びは、今後は生徒たちから教えてもらうことの方が多いかもしれません。
――説明会で実際に子どもたちの様子を見て、開校の実感が湧いたことと、準備員会で得た経験を今後に生かしたいということが、3人に共通していることだと感じました。では、それぞれの教科の観点で、どのような学びを提供したいとお考えですか?
Gさん:生徒同士が関わり合う中で、体を動かすことが楽しいとか、心地いいなと感じたり、チームで一緒に取り組むことで楽しかったと感じたりする経験を提供したいです。
――それはなぜ?

Gさん:ものづくりに関する多様な興味関心をもつ生徒が集まるように、運動についても得意不得意など生徒それぞれだと思っています。そのため、得意な子が目立って、苦手な子が引っ込むのではなく、マット運動などの個人競技であっても、チームで教え合ったりすることで、競技への関わりを自主的に持てるようにしたいです。
このような経験から、運動を通じて心がすっきりしたとか、落ち着いたと実感し、生涯を通じて運動することの意義を感じ取ってほしいです。
――関わり合いをデザインするときのコツはありますか?
Gさん:いろいろ試しながらではあるのですが、やはりチームで誰かが方向性を示してくれると、話がスムーズに進みますね。人間関係に依存する場面もあるため、深く関わろうとすると週3時間の体育の時間だけで完結することは難しいところもあります。しかし逆に、体育のチームは種目ごと、さらに授業ごとにチームを変えることができるため、リーダー性を発揮する機会を数多く設けることができます。前の授業では率先してできなかったけど今日は、というように小さなチャンスが毎回あると思っています。
そこで、「みんなどう思う?」というような声掛けから、それぞれの意見を出し合って、「じゃあ次は、こうやってみようよ」という流れでチームが進んでいく経験をするだけでも、普段のクラス活動で一緒のチームになったときにしゃべりやすくなるのではないかと考えています。それが自律的な学校生活の中で、主体的に行動することにつながると思います。
――数学はどうでしょうか?

Sさん:私もTさんがおっしゃったように、中学校卒業後は工科高校に進学することを見据えて、身近に数学を使う場面というか、数学がこの部分の役にたっているとイメージしやすいところを見せたり、話したりしたい。そして、工学において数学は道具だと思うのですが、なぜ道具なのかは、数学の授業が一番伝えやすいと思うので、このなぜという疑問を持たせるような授業を行いたい。「この式の定義はこれで、成立条件はこうだよね。」という会話が生まれたら面白いと思っています。そして、新しい疑問や発見を通して学びを深めてほしい。
Tさん:準備員会でSさんとお話しする中で、中学校の数学の学習内容に比べて高校の数学は内容が多いと感じました。ひとつの単元が終わったらすぐ次の単元というように追われているような。そのため、中学校の数学では、学習している中で身近な工業のものなどに結びつける時間を確保して、高校進学後に生かせる基礎基本の定着について工夫したいです。
――数学では少人数展開で授業を行いますが、現段階でイメージはありますか?
Sさん:生徒それぞれが、自分の意見を言いやすい環境になると考えています。それに対して教員だけでなく、生徒同士も、それを聞いてどのように感じたかや、質問などもやり取りがしやすくなることが魅力だと思います。体育のGさんのお話でもあった通り、関わり合いの中で自主性が育ち、協働する姿勢も育まれるのではないでしょうか。

Tさん:これまで私は黒板に例題の解き方を書き、一方的に伝える授業を行うことが少なくありませんでした。しかし今はできる限りファシリテーションに徹するというか、流れよく見て、子どもたちに考える余白を意識的に作ることができるようになってきました。より発展的な問いを自発的に生み出す生徒も現れて、今まで体験したことのない授業展開となっています。愛総中での少人数授業では、この経験をさらに加速させることができるのではないかと考えています。
――みなさんがこのような考えに至った原体験があれば教えてください。
Gさん:体育の授業で生徒が楽しいと感じる瞬間が、勝敗ではなく、授業展開の過程にあると感じたことです。チーム運営や、ルール設定を生徒自身に任せることが多いのですが、競技が得意な生徒も不得意な生徒もみんなが楽しむことを目標にすることで、1つのチームとして話し合い関わっていく中で、授業を生徒全員で作り上げたという充実感が得られて、楽しさに繋がっているようです。苦手な生徒も、自分たちで考えたルールだから積極的にチャレンジできる、そんな環境が生徒たちの求めるものかもしれません。
――自分たちで考えたルールだからこそ、競技に没入するハードルが下がり、実際やってみて、「楽しかった、体を動かすっていいじゃん」というポジティブな感情のループを生み出しているようですね。
Tさん:今取り組んでいる、探究的な数学の授業において、子どもたちにどうやってこの問題を解決するのかと問うたり、この言葉はどういう意味があるのかと質問したりして、できる限り自分たちで答えらしきものを見つけさせています。この活動を通して、生徒と共に私自身学ばせてもらっていることにとても充実感があります。そして毎授業の最後には、疑問や気になることを振り返らせているのですが、次の授業につながる課題を私がピックアップして、そこから授業を始めています。
Sさん:工科高校に勤めていて、私自身電気工事士の試験を受ける機会を得ました。そこで工学的に数学が活用されているのを身をもって体験したこともあり、授業の中で意識的になぜ数学を学ぶのか、なぜこうなるのかなど、問いかけることを意識しています。
――最後に、来年4月に開校する愛総中は、どんな学校になると思いますか?
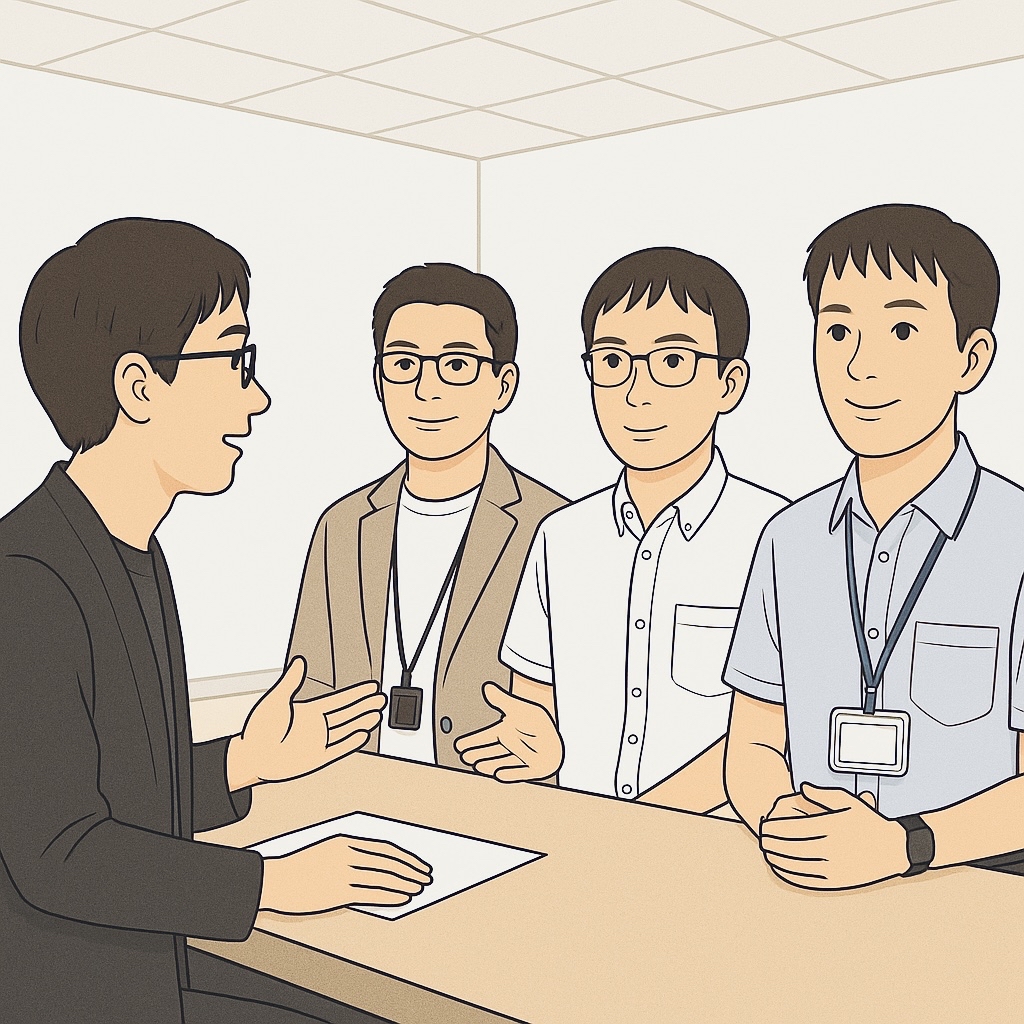
Gさん:ワクワクする学校だと思います。チャレンジ100もそうですが、準備をしている私たちも、来年の今頃どうなっているのかとワクワクしています。きっと準備で100%完成させることはできなくて、学校の主役である子どもたちと本当の意味で作り上げていくことになると考えています。
このインタビュー中もワクワクしているし、どんな子どもたちと一緒に生活して、どんな毎日が待っているのだろうとワクワクが止まりません。
Sさん:教員も生徒も未知なものに進んでいく。道の草をかき分けて進んでいく学校なのかなと思います。高校は今年創立10周年で、私は9年勤務していますが、毎年何かしら新鮮味を感じています。きっとその新鮮味はこれからも続いて、日々それを感じながら送る学校になっていくと思います。
Tさん:教師目線で言うならば、愛総中で未知なモノ・コトに触れて、自分の教員としての幅を広げられるような気がしています。また、子どもの目線で言うのであれば、自分たちが学んだり、つくったりしたものがどこで生かされるのか知ることで達成感が高まり、学びも深まると思います。そのため、教員も子どもも自分たちの可能性を、最大限に引き出せる学校になるのではないでしょうか。
――今回三人のお話を伺って、人と関わり合う中で自分自身について理解し、それを表現することが、自分だけでなく周囲の学びを深めることにつながると感じました。
愛総中の数学・保健体育の授業についてお話しいただき、ありがとうございました。
Gさん・Sさん・Tさん:ありがとうございました。
